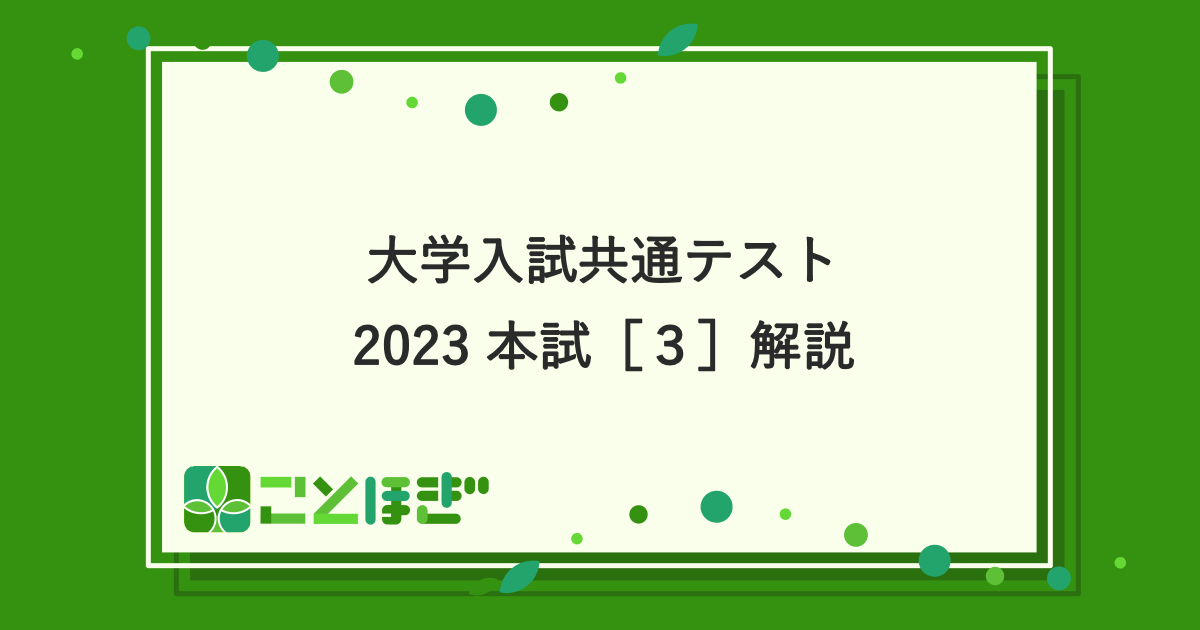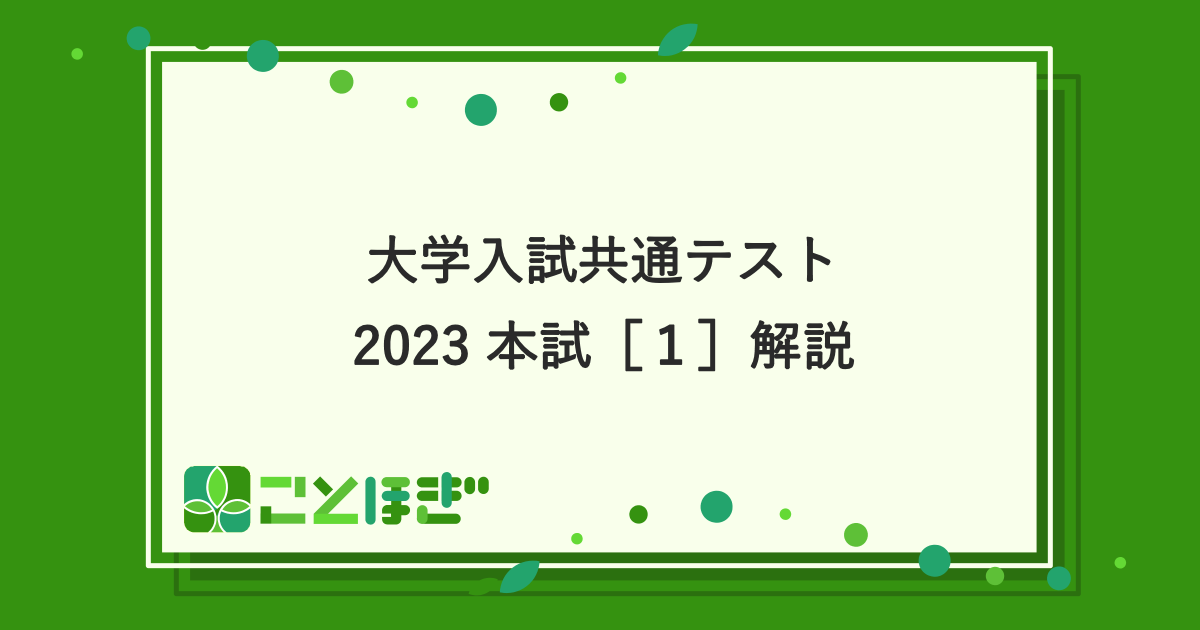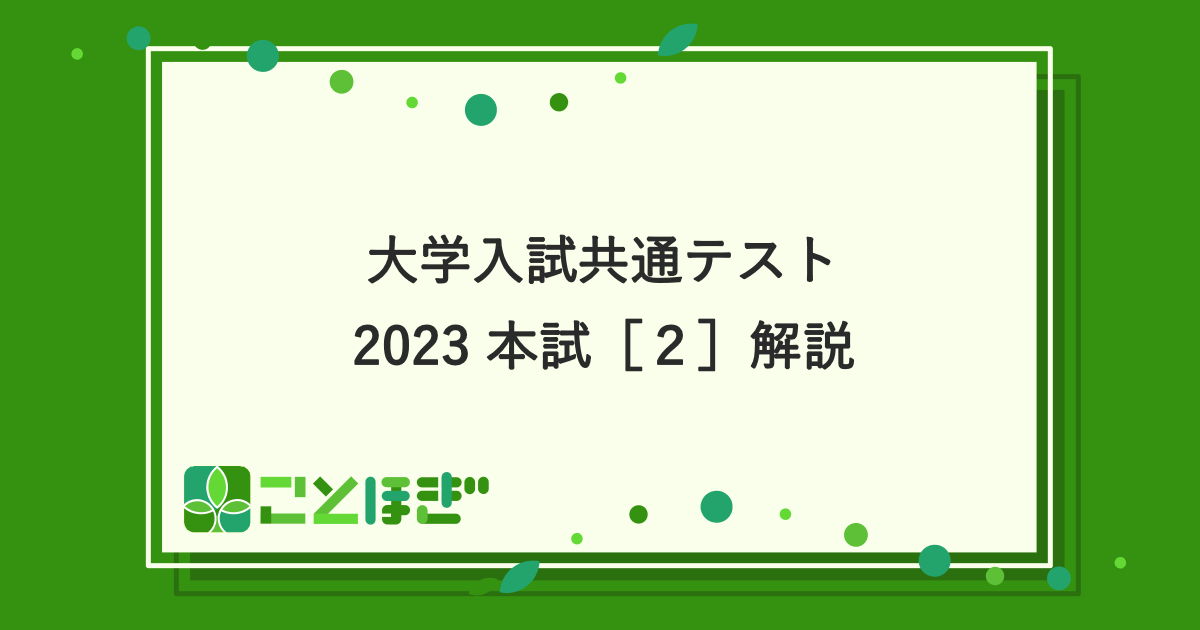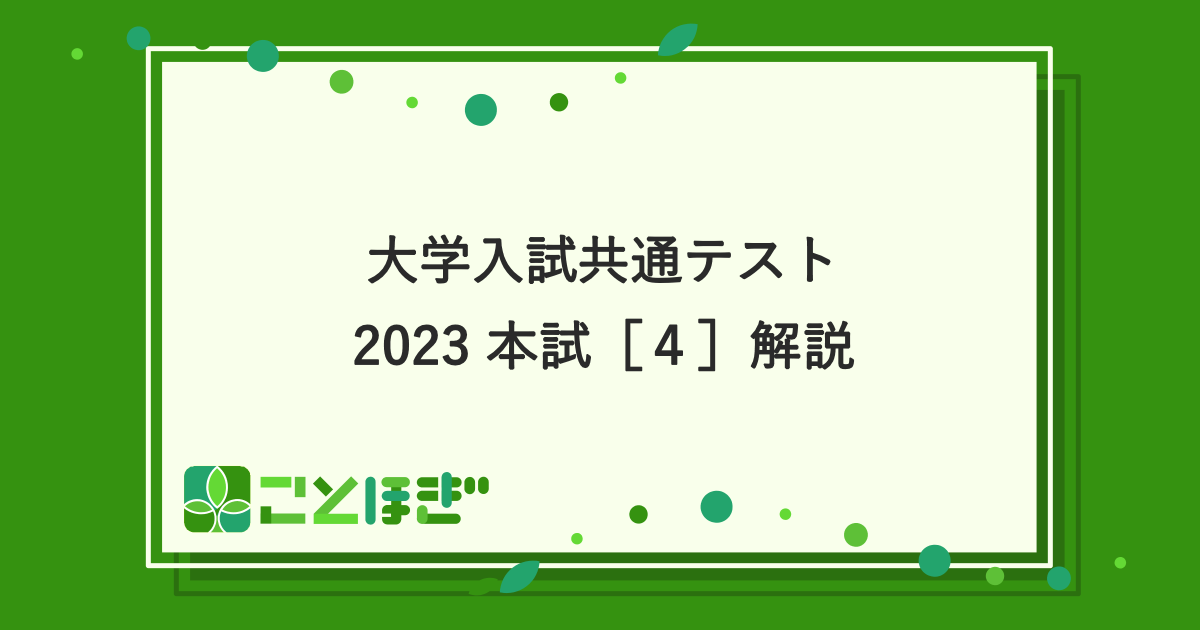解説
ご留意
選択肢の吟味において、「×・△・?」を選択肢の該当箇所に付けていきます。×は「これはちゃうやろ」、△は「ちゃうかもしれん」、?は「びっみょ〜」って感じです。結局は△と?がついた箇所の吟味となることがほとんどです。
あと、私が解答作成前に解いて間違えたところは正直に言います(かなしいけど)。ちょっとご参考にください。
問1
(ア) 正答③
「さしまはす」はあまり一般的な古語ではありませんが、注釈2にあるように、「船を操作する人」を「船さし」と言っています。棒を水底に挿して船を押し動かす人、のような感じではないでしょうか。ここから「さしまはす」も推測できそうです。
選択肢の吟味
①「さりげなく」は「やうやう」の訳語として不適切です。また、「〜と」も「程に」の訳語として合いません。
②「あれこれ」は「やうやう」に合いません。
③正答です。
④「集まる」は「さしまはす」に合いません。また、「〜と」も不適切です。
⑤比較的近いですが、「さしまはす」を「演奏が始まる」と訳すのは少し考えづらいです。
(イ) 正答④
「ことごとしく」の訳語と、「歩みよりて」が誰の方になのかから判断します。歩みよる主語は「若き僧(良暹の傍らにいた僧)」ですが、これは良暹の句を船の上の殿上人に伝えにいくシーンですので、歩みよる方向は「良暹の側→殿上人の方」です。
選択肢の吟味
①「たちまち」も「ことごとし」とは違います。「僧侶たちの方」も方向が違います。
②「焦った様子で」が不適格です。
③「良暹のそばに来て」が間違いです。
④正答です。「ことごとし(事々し)」は「大仰な様子」「大袈裟な様子」などが定訳ですが、「もったいぶって」も良いと思います。
⑤「良暹のところに行って」が違います。
(ウ) 正答②
「かへすがへす」は「何度考えても」がよくある訳です。何度考えても結論が変わらないことですので、②「どう考えても」になります。
①の「繰り返すのも」が比較的行けそうですが、文脈として「わろきこと」と言われているのは「これ(良暹の上の句に対する下の句)を今まで付けぬ(こと)」であり、「下の句をまだ付けられていないことは、どう考えても良くないことだ」という意味になります。「繰り返すのも」とすると、「わろきこと」の対象が複数になってしまい文が通りません。
問2 正答③
文法の問題です。文法は文意を正しく捉えるためにかなり大事なので、文脈を読めるようになることと相乗効果としてできておきたい問題です。
選択肢の吟味
①「若から/む」で、ク活用形容詞「若し」未然形+婉曲の助動詞「む」の連体形です。
②「侍り」は確かに丁寧語ですが、台詞の中に含まれる場合、その話者が向かい合っている人への敬意ですので、若き僧→殿上人の敬意です。
③正答です。こんな感じで、地の文において筆者がいきなり「こんな感じなんかな?」と推測しだすことがあります。今回は、良暹が上の句を詠み出すのが早かったので、「準備してたのかな?」と筆者が言っています。
④「今/まで/付け/ぬ/は」で、「ぬ」は打消の助動詞「ず」の連体形です。「付く」が下二段活用で未然形と連用形の区別がつかず、上で判断できませんが、「ぬ」の後に「は」が続いており、「付けない(の・こと)は」となっていますので、もし強意の「ぬ」なら連体形で「ぬる」になっているはずです。
⑤「覚えずなりぬ」の「なり」は動詞の「なる」の連用形です。「わからなくなってしまった」の「なる」部分を担っています。
問3 正答 ⑤
特定の傍線部ではなく、広く内容について問うています。該当する箇所を断定するところから始めないと行けないので、広く適切にサクサク読む必要があり、ちょっと大変です。
選択肢の吟味
①「当日になってようやくもみじの葉で飾った船を準備し始めた」が×です。第一段落より、「紅葉を多くとりにやりて、船の屋型にして」から「その日になりて」となっていますので、準備してから当日を迎えています。
②「時間が迫ってきたので、祈禱を中止し」が△です。宇治の僧正は確かに祈禱のために普賢堂に来ていたのですが、そのタイミングでまさに祈禱していたのを取りやめて、庭に僧を集めたとは書かれていません。ただこれが一番迷った選択肢でした。
③「船に乗ることを辞退した」が△です。良暹を船に乗せない(「あるべからず」)ことを決めたのは殿上人たちです。また、「喜びを感じていた」も直接的に描かれていません。
④「管弦や和歌の催しだけでは後で批判されるだろうと考え」が×です。殿上人たちが後に批判されるかと懸念したのは、身分の低い(殿上人ではない)良暹を船の上に乗せることです。
⑤正答です。「平がりてさぶらひければ、かたはらに若き僧の侍りけるが知り、『さに侍り』と申しければ」が該当します。良暹が平伏していたので、側にいた若い僧が気づいて「そうでございます」と申し上げた、ということです。
—–スポンサーリンク—–
————————
問4(i) 正答④
掛詞まで教えてくれるなんて優しいなァと思いながら読んでいました。選択肢を読む前に、ある程度当該箇所の解釈を試みましょう。
和歌の解釈の際には、必ず五七五七七で区切りましょう! 今回は、「釣殿の/下には魚(いを)や/すまざらむ」「うつばりの影/そこにみえつつ」です。上の句は「すまざらむ」であって、「やすまざらむ」ではない点に注意です!
選択肢の吟味
①「皆が釣りすぎたせいで釣殿から魚の姿が消えてしまった」「昔の面影をとどめている」が△です。和歌内で特にそんなことは述べられていません。
②「心を休めることもできないだろうか」が△です。「やすむ」ではありません。
③「『すむ』に『澄む』を掛けて」が×です。「澄む」を掛けているのなら、「すまざらむ」は「澄んでいない(澄まない)」になるはずです。「澄み切っている」と掛けていると捉えるのはさすがに恣意的すぎます。
④正答です。いい感じに詠んでます。
問4(ii) 正答①
一つ前の問題を受けて、掛詞も併せて考えていきましょう。
選択肢の吟味
①正答です。「焦がれる」で「葉が色づく」を表しているというのがやや慣れませんが、「葉が日に焼ける」に近いものがあるのかと思います。
②「寛子への恋心を伝えるために詠んだ」が△です。選択肢としてはなんかいかにも古文にありそうな話なのですが、良暹が寛子に恋心を抱いているという根拠が一切なく、さすがに厳しいです。
③全体的に厳しいです。掛詞もうまく表現できていません。基本的に、和歌中の含意は和歌の中に含まれるパーツから推測するか、和歌が詠まれる状況を踏まえて推測するかのどちらかです。当該の上の句が、藤原家の栄華を讃える文脈にあるとは言えません。
④こちらも全体的に厳しいです。「マ行の音で始まる言葉を重ねることによって〜心を癒したい」というのも、かなり無理矢理な感じです。私は言語学を専門としていましたが、マ行音に心を癒す効果があるなど言えば、音声学の人に怒られてしまうと思います。笑
問4(iii) 正答③
こちらも第四〜第五段落の内容を広く取っていきます。基本的に、良暹の上の句に対して殿上人たちが適した下の句を付けられなかったという点を押さえておきましょう。
選択肢の吟味
①「良暹を指名した責任について殿上人たちの間で言い争いが始まり」が△です。「『いかに』『遅し』とたがひに船々あらそひて」とありますが、これは下の句を付けられないことに関して「どうしようか」「もう遅い」などと言い合っているところなので、「良暹を指名した責任」を問うているものではありません。
②「寛子のための催しを取り仕切ることも不可能だと悟り」が?です。催しを取り仕切っていたのは、殿上人というよりも、どちらかといえば宮司たちです。
③正答です。第五段落は殿上人たちが船から降りるところ〜降りた後の様子が描かれていますが、周りの人はみんなバラバラと席を立ち、殿上人は逃げ帰るように立ち去っています。
④「宴も殿上人たちの反省の場となった」が×です。上述の通り、船から降りた殿上人たちは皆逃げ帰るように立ち去っていますので、宴で反省をしたとは言えません。
読解後のつれづれ
比較的短めの課題文でしたが、その分対話文がありました。掛詞のヒントをくれたり、優しい先生でしたね。
途中、良暹と殿上人の身分差について触れましたが、良暹の身分が低いというよりは殿上人の身分が高いと思っておいてください。殿上人って、古文ではやたらと出てくるポピュラー寄りな存在ですが、身分としてはかな〜り高い人たちです。そもそも一般の人たちは会うことも到底できないようなもんです。
今回も殿上人たちがやや醜態を晒すお話でしたが、俊頼も少し気を遣っているのか、殿上人たちの個人名を書いていません。そういうところもなんとなく古文の妙という感じがしますね。
今回の私は満点でした(よかった〜)。今回もお疲れ様でした!